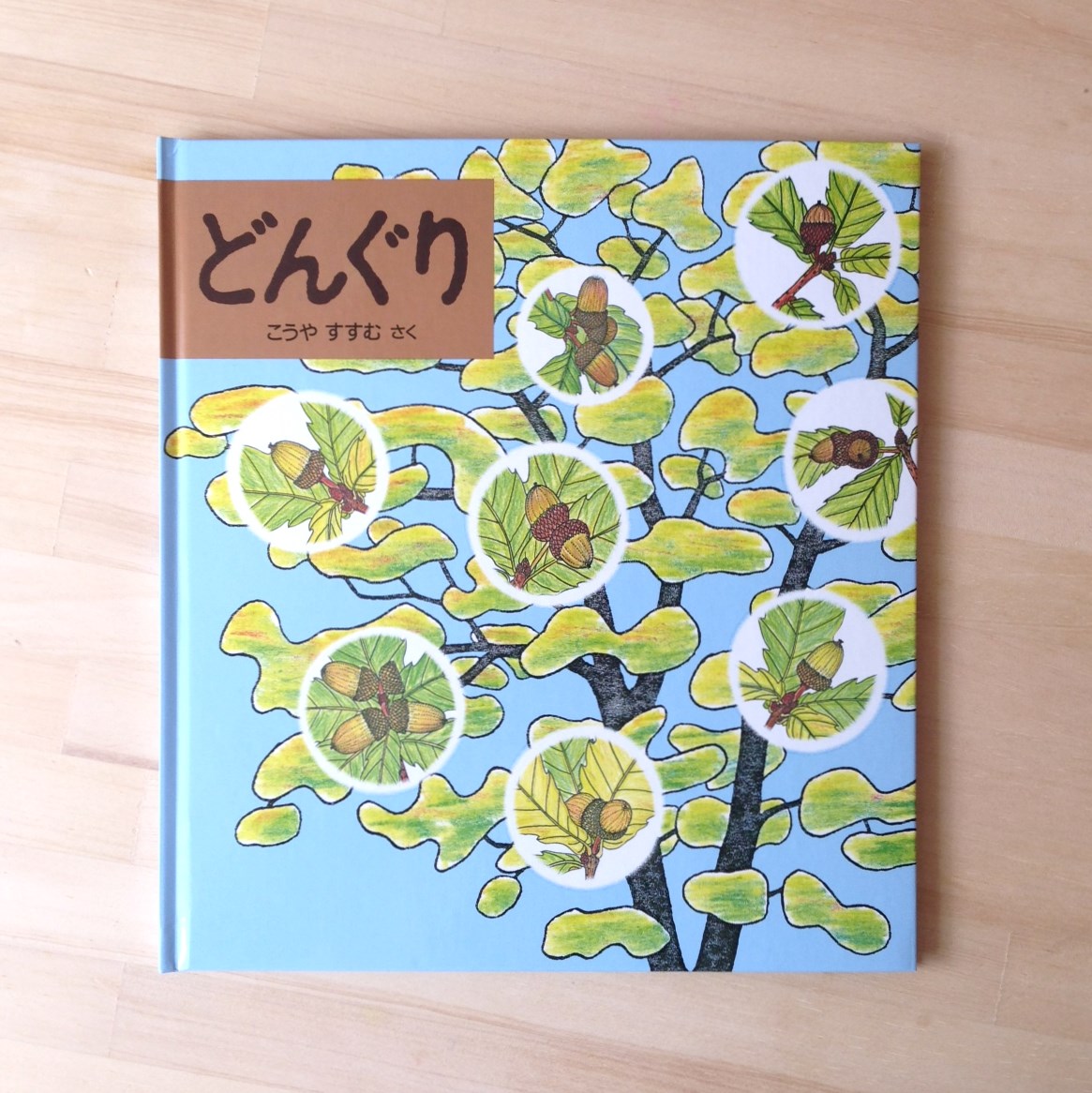『かみひこうき』 文 小林実 絵 林明子 出版社 福音館書店 発行日 1976年4月1日 ※月刊「かがくのとも」1973年11月1日発行 価格 ¥900+税 いろんなかたちの紙飛行機。 とがった飛行機は、びゅーんと真っ直ぐに飛ぶ。 つばさの広い飛行機は、すいーっと輪をかいて飛ぶ。 それじゃあ、どんな風に折っているのかな? バランスよく飛ばすには?宙返りをする飛行機を作るには? 墜落飛行機は、どこをどうやって直したらいいのかな。 紙飛行機の折り方や、そのコツを分かりやすく紹介した、紙飛行機の入門書のような1冊です。 * * * * * * * 今日は、11月11日。 調べてみると、「いただきますの日」、「靴下の日」、「煙突の日」など、お馴染みの記念日以外にも、たくさんの記念日があるそうです。 その中に、「おりがみの日」というのがありました。 東京おりがみミュージアムのホームページ によると、 “ 数字の1が4つ並ぶ11月11日、数字の"1"を正方形の一辺と見立て、1が4つで正方形のおりがみの4辺を表すことから、1980年、この日を「おりがみの日」に制定しました。 この日は世界平和記念日(1918年第一次世界大戦休戦条約が調印された日)にもあたり、おりがみの平和を願う心と相通じるものがあることも制定した理由のひとつです。 ”とのこと。 ほほう、なるほど・・・。 それならばと、今日はこの1冊を選びました。 この本で紹介されている基本的なおり方は2パターン。どちらもよく飛びますが、このパターンに少し手を加えたり、工夫をするだけでも、いろいろな紙飛行機が作れます。 さっき、折ってみました。 私も、久しぶりにこの本を見ながら折ってみましたが、やっぱり良く飛びます。 ちなみに、ここで紹介されている折り方では、長方形の紙を使っています。チラシやコピー用紙などを使うか、色紙の場合は、幅を4分の3くらいにカットすると良いかと思います。 もちろん、長方形以外の形でも、良い飛行機ができるかもしれません! たくさん挑戦して、とびきりの飛行機を作ってくださいね。